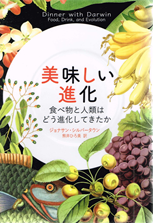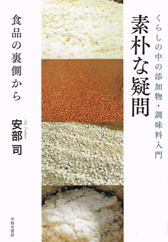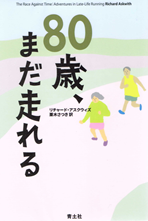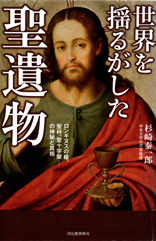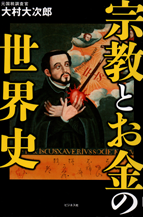柴田哲孝「暗殺」
シルバータウン「美味しい進化」
安部司「素朴な疑問」 柴田哲孝「暗殺」
この本を図書館で予約したところ、予約待ちが20件以上あって数ヶ月待った。ノンフィクション的な要素を期待するとかなり当てが外れるが、いろいろ考えさせられる作品であった。 考えさせられたのは、いまの日本で陰謀が成り立つかということである。もしかすると「いまの」は不要かもしれない。日本人は陰謀を仕組むほど洗練されていないし、そういう知恵者もいない。スケールが全然違うというのが正直なところかと思う。 黒幕とか実力者、フィクサーとされる人達は現実にいる。しかしそういう人達にできるのは不作為、握りつぶしてなかったことにするくらいで、せいぜい許認可に手心を加える程度である。複数の組織・人物を意のままに動かし、偶然も含めて望む方向に誘導する力までない。 正規の指揮命令系統であっても、県警相互の連絡が不十分で、グリコ森永事件で実行犯を取り逃してしまうのが日本である。表沙汰にできない目的・意図で、警察・自衛隊・政治家・報道関係・宗教団体を差配するなんてことが、残念ながらできるはずがない。羊でも入っていればともかく。 もしかするとそういうことが意図的にできたのは信長・秀吉が最後で、以後500年間日本では出現しておらず、だから彼らが偉人とされるのであろう。 明治維新はもともと外圧だし、第二次大戦は純然たる外圧である。著者の出世作である下山事件も、GHQが絡んでいなければ完全犯罪にはならなかっただろう。 本の紹介に戻ると、これは安倍元首相狙撃事件を題材とした小説である。迷宮入りした朝日新聞支社銃撃事件との関連については新味があるけれど、さまざまの要素を含めすぎて、一冊の本としてはまとまりに欠ける。一番違和感を感じるのは、そんな実力者はいないということである。 そして、この陰謀は選挙日程等々の要因により当初予定から2年近く遅れることになるが、その間関係者が健康問題も起こさず、組織への発言力も衰えず、狙撃者はゴルゴ13並みの腕前のままで(みんな年寄りなのに)、誰一人秘密を洩らさないなんてことはありえない。 著者としては、あからさまにノンフィクション仕立てにすると命が危ないというメッセージのつもりかもしれないが、作者は私と同じ歳である。何年続くか分からない余命よりも、完成した作品を残すことの方が優先順位が上なのではなかろうか。 繰り返しになるが、他殺の可能性が大きい事件を握りつぶして事故や自殺で処理することのできる黒幕・実力者・フィクサーはいるだろう。鑑定結果の内容を変えることは、幾多の冤罪事件で実際に行われている。 しかし、数多くの関係者を意図的に動かして、その秘密が漏れないし何かの偶然で齟齬を生じることもないなんて人間わざではない。湘南の豪邸で政財界に影響力を及ぼすくらいは、世界レベルでみれば農協理事長か町内会役員くらいのことに過ぎない。私だってできるとは言わないが。 安倍元首相狙撃事件を題材にした推理小説。著者の他の作品のようにノンフィクション的な要素を期待すると少し期待外れだが、いろいろ考えさせられた。 シルバータウン「美味しい進化」
原題 "Dinner with Darwin"「ダーウィンと夕食」である。軽い本のようにみえるが、中身は最新知見が満載された進化の本である。 わが国では、博士号を持っている専門医でさえ、理系の知識は小学生並みと思わせるような本を書いている。中性脂肪は脂肪の摂取が原因で増えると書く(それだけでなく診察で患者に言う)始末で、専門医だからといって正しい知識を持っているとは限らない。 だから、農耕以前の人間は肉食だったと糖質制限の本に書いてあったりする。だったらなぜ腸がこれほど長いのかと聞きたくなるのだが、さすがにこの著者は生物学、進化生態学の教授なので、裏付けがきちんとしている。 腸の長さもその根拠だけれど、人間がもともと草食・穀物食であったことは、甘味と苦味を感じることに表れているという。 甘味は、糖質を多く取り入れようとする進化の過程で選択されたもので、ネコは甘味を感じない。肉食動物は、糖質を選択する遺伝情報が残らなかったのである(チュールが好きなのは甘いからではなく、肉のたんぱく質を感知するから)。そうしたことは、ネコに甘いミルクを飲ませて調べたわけではなく、ゲノム分析で甘味を感じる遺伝子がないことで分かった。 苦味を感じるのは、植物が自衛のため備えている毒物(アルカロイドなど)を察知するためである。かつて草食であったから、食べられないものを区別するため進化の過程で苦味を感じる遺伝情報が残った。これらの知見は、ゲノム解析の進展により21世紀に入って明らかになったことである。 類人猿のほとんどは草食で、主に食糧とするのは植物の根茎や葉、実である(貝や魚を食べることもあるが主として植物)。それが現生人類に近づくにつれ、肉食との雑食になる。それはいつ、なぜ起こったのか。ヒト属のどの段階からかを考察したのがこの本である。 ゲノム解析以前には、住居の焼け跡から調理の痕跡を調査したり、化石に残された食物の痕跡を探るしかなかった。ところが現在は、遺伝子が現人類にどう残っているか、また近似する生物(類人猿、哺乳類、陸上生物、etc.)との遺伝子比較から、いつ、どの段階で獲得された資質か判明するのである。 これによると、肉類を食べられるようになったのは、調理との関係が深いらしい。最初は偶然だったと思われるが、生肉を焼くことにより、健康被害(食中毒や消化不良)も防げるし保存することもできる。少なくともネアンデルタール人は、肉を焼いて食べていたらしい。 発酵という調理方法も、現人類よりはるかに起源は古い。乳酸菌もアルコールも、工業化以前に自然の力でできるものだから、人類以前にも発酵食は利用されてきた。木のくぼみにできた果実酒を飲んで愉快になったのは、ヒト属よりかなり古くからである。 遺伝子を調べると、オランウータンは酒を飲めないが、ゴリラは飲めるらしい。人間でも、アルコールを消化できる人といない人、牛乳を消化できる人とできない人がいる。それがどの段階で生じたかを調べると、進化の面白さが垣間見られる。 [Feb 19, 2025] 題名だけでなく表紙イラストも軽い読み物を想像させるが、中身はしっかりと進化について論じている。竹内久美子とは格調が違う。 安部司「素朴な疑問」
食品添加物については、数十年前から懸念され、いろいろなところで指摘されている。著者は食品メーカーで添加物を使った商品開発の第一線で活躍してきた経歴の持ち主で、添加物を使えば何ができるかの知識は抜群である。 そして、講演会で女子中学生から受けた素朴な疑問「なぜ甘いのにカロリーがないんですか?」に対する回答に、私自身の長年の答えを見つけたような気がした。「食べ物じゃないからです」 (なお、本書のセリフ部分はすべて九州弁で書かれている。これを好ましいと思うか不愉快に感じるかはひとそれぞれだろう。私は標準語で引用する。) 前回書評で取り上げた「ダーウィンと夕食」に書かれていたように、もともと甘さを感知するのはカロリーの高い食物を識別・摂取するためである。それが個体の生存に有利なので、甘さを感知する遺伝子が生き残った。逆にいうと、甘い食物を感知できない人間は生き残れなかった。 それがいまや、人間が「脳」をあやつり、カロリーのない食物を甘いと認識させている。これが進化なのか退化なのか不明だが、食糧難になれば生き残りに不利になることは間違いないように思う。 初期の「美味しんぼ」にあったように、いまの味噌・醤油はもはや常温で保存できない。食通を満足させる味は伝統的な製法でしか作れないという主張だったが、海原雄山曰く中華料理は中国の調味料でなければ本来の味でないというから怪しいものである。中国の酢や醤油は日本以上に添加物満載である。 話は戻って、「添加物は食べ物ではない」という著者の主張で思い出したのは、ずっと昔、びっくり人間みたいなTV番組で、ガラスを食う人間がいたことである。人間はガラスを消化できないので(バクテリアとかじゃないと無理)、きっとギャラのために危ない橋を渡ったんだろう。 また、昔津田沼にあった(いまイオンがある場所)人工スキー場の営業担当が、やはりTVで、プラスチックの雪代替物を「食べても何ともありません」とむしゃむしゃ食べてみせたこともあった。食べ物でなくても食べることはできるが、体によくないことは間違いないし、いいことは断じてない。 すべてとは言わないが添加物のかなりの部分は、基本的にガラスやプラスチックと変わらない。急性毒性はなく発ガン性も確認できていないけれども、だからといって健康に害がないとは断言できない。 著者は添加物を加えるメーカーを批判するのは筋違いで、それを買う消費者がいるからだと言うけれども、技術進歩をカネに代える発想が根本にあるからそうなる。そして、安くておいしくする添加物や長持ちさせるだけではなく、そうした役割を何ら果たさない見栄えだけの添加物も世の中にたくさんある(ジュースとかハムとか)。 著者はスーパーに行ったら手首の運動が欠かせないと言う。POP広告なんて、メーカーに都合のいいことしか書いてない。この本を読んですぐ、奥さんがカロリーハーフのマヨネーズを買おうとしたので「それ、マヨネーズじゃないよ」と指摘したらびっくりしていた。 「同じ入れ物なのに、マヨネーズじゃないの?」。マヨネーズだからといってどんな卵を使っているか分かったものではないが、卵も油も酢も使わないドレッシングをマヨネーズとは呼べない。コーヒーフレッシュやラクトアイスと同様、ガラスやプラスチックと似たようなものなのである。 [Mar 14, 2025] 食品添加物については数十年前から懸念されているが、この歳になるとこれまでとは違った見方になる。何がよくないかではなく、どこに優先順位を付けるかだと思う。 キャサリン・イーバン「Bottle of Lies」
邦題「ジェネリック医薬品の不都合な真実」。内容はそのとおりなのだが、不都合な真実がアル・ゴアではなくインド企業の片棒を担いだクリントンを揶揄している点が分かりにくく、原題の方がよく本書の特徴を示しているように思う。ただ、翻訳はたいへん読みやすい。 インドのジェネリック製造会社ランバクシーが、米国FDA(食品医薬品管理局)に虚偽のデータを送って審査を通り、世界中に有害な医薬品が販売されたスキャンダルの経緯をまとめた本である。インドといえばいまや日本を上回るハイテク国家であり製薬国家であるが、前近代的要素が多分に残されている国でもある。 それは、YouTubeでインド屋台料理の動画を見ても分かるのだが(基本的に生ゴミは道路に放置で、ハエが飛び回っている)、シリコンバレーでは多くのインド人技術者が働いており、米国の大学や研究機関にいるインド系研究者は日本人よりずっと多い現状とはかなりのズレがある。現実はどちらに近いかというと、後者とはなかなか断定できないようだ。 この本では、21世紀はじめにジェネリック医薬品のブームが起きて以降の動きから話が始まる。リピトールやアトルバスタチン(私も飲んでいた高脂血症薬。後者がジェネリック)といった聞きなれた名前に興味を引かれて読み始めると、次に出てくるのはインド企業の縁故重視・収益最優先という前近代性であった。 コンプライアンスは絵空事という、かつて自分がいた職場を思わせるような記述が続き、前近代的な社風はどこの国でも似てくるものだと思った。そして、そのインド企業ランバクシーは、米国FDAに義務付けられた多くの規制を、虚偽のデータ、つまりコピペでかいくぐって認可を得たのであった。 まるでかつてのリケジョを思い出させるようなやり方だが、ランバクシーは有害・欠陥製品を世に出したのだからもっとたちが悪い。この事件では米国市場に出たので問題となったが、アフリカや発展途上国にだけ出荷したのであれば、いまだに続いていたかもしれない。 日本では厚労省がちゃんと管理しているから大丈夫ということはない。確かに最終製品(糖衣錠にする等)は日本国内で製造されているものがほとんどだが、原剤と呼ばれる有効成分は、いまや中国やインドで作られているものがほとんどなのだ。 だから、問題企業のランバクシーも、第一三共が買収して子会社化し、その後にFDAとのトラブルが表面化した。第一三共もこの本の後半では重要な登場人物となるのだが、いくら専門知識・商品知識があったとしても、言葉が通じなければ難なく騙されてしまうという見本みたいなものである。 「盗人にも三分の理」的な見方をすれば、データが捏造だろうと製造工場が不衛生であろうと、最終製品である薬がちゃんと効けば問題ないかもしれない。この事件でも、最終的には和解(賠償金)という民事的解決が図られていて、刑事罰が科された訳ではない。そのあたり、やや消化不良的な読後感は否めない。 そして、煩雑な手続きが薬価を高めているのはそのとおりなのだが、だからといって諸手続きを無視・捏造していい訳ではない。それは、過去の重大な薬害事件の反省から厳格化されているからだ。サリドマイドも、エイズ血液製剤も、私が生きている間の事件である。 この本から教訓とすべきなのは、医薬品の検査は基本的に製造プロセスの検査であり、どんなに厳格化してもロットによるばらつきは避けられないこと、その結果として、自分の手元にある薬はどうやっても100%の信頼性はないことである。 薬効は取説に書いてあるより少なく、副作用は多いことを肝に銘じなければならない。だから飲み薬だろうがワクチンだろうが、本当は避けた方がいい。どんなに先進国の規制が厳格であっても、有効成分は中国やインドで作られている。彼らがどういうモラルなのか知るすべはないし、そんなことにリスクは取れない。 リケジョのようにデータをコピペして米国FDAの認可を得たインド・ランバクシー社のスキャンダルをまとめた本。ランバクシーに騙されて数千億円で買収してしまった第一三共も登場する。 リチャード・アスクウィズ「80歳、まだ走れる」
マラソンの本は黙って俺の言うことを聞けだし、ネットの記事はアクセス狙いの無責任なものばっかしである。私が聞きたい話はないのかと思っていたら、この本はすごく参考になる。マスターズ陸上がテーマだから、まさにターゲットど真ん中である。 はじめにフェル・ランニングという聞きなれない言葉が出てきて(トレランとクロスカントリーの中間らしい)、著者のケガの悩みや心身の衰えから話が始まるのでやや退屈だが、途中からマスターズ陸上選手のインタビューになり、そこからは息つく間もなく終盤まで読み進めた。 読み応えのある本だし、日本のスポーツ指導者が書くランニングの本よりずっと納得できる。「インターバル走は不要だと私は思います」というのと、「スピード練習は必要よ。年取ると筋肉がどんどん落ちてくるから」と、どちらがより説得力があるかということである。 日本はマスターズ陸上の先進国で、世界記録保持者もたくさんいる。「W60サブスリー」弓削田さん「M90スプリンター」田中さんをはじめ、世界的にトップクラスの選手は数多い。本書でインタビューしている中野陽子さんも、その中のひとりである。 まさに中野さんがそうなのだが、マスターズ選手の中には老齢になるまで陸上競技未経験だった人達がいる。著者に言わせると「いまの私の歳には市民ランナー、それも初心者だった」のである。そして、経済的に恵まれている人ばかりではない。それまでの半生も、競技を始めてからも、生活の苦労は変わらなかったのである。 「マスターズ陸上のルールその1は、ケガをしない。その2は、ルールその1を忘れない」 「高年齢になってキャリアをスタートしたランナーのいいところは、自己ベストを長く更新できること」 「毎週、毎月、毎年続けていれば、ある日突然力が付く。日々の前進は微々たるものに過ぎないが、とにかく辛抱強く取り組まなければならない」 これらのことを述べているのは、少なくとも70歳以上であり、中には80歳90歳のランナーもいる。それでも、日々の努力を続けなくてはならないと言うのだ。70前などヒヨッコもいいところで、元気づけられるとともにもっと精進しなければと思った。 この本の終盤で、走る哲学教師が出てくる。彼は走るようになって(そして体を壊して)から、ニーチェやカミュが何を言っているか理解できるようになったという。 努力したからといって必ずしも結果や成果に結びつく訳ではない。造物主や運命は、個人個人が何をしたかなんて見ていない。それが不条理ということなのだ。 それでもわれわれが努力するのは、シーシュポスが山頂に巨石を押し上げるのと同じことである。いずれ力尽きる時が来るし、山頂まで押し上げた石は再び谷底に落とされることになるが、だからといって押し上げる行為に意味がないことはない。 われわれも何かに向かってトレーニングするけれども、それが好記録になるとか、注目されるとかはどうでもいいことである。マスターズの選手たちはタイムとか順位に関係なく、走っていること自体が楽しくて仕方ないし、ゴールは至福の時である。何歳になっても、全力を尽くせるのは幸せなことなのだ。 マスターズ陸上で実績を残したランナーの中には、高齢になってからランニングを始めた人もいる。そういう事実を知るだけでも励みになる。 水木しげる「ラバウル戦記」
お盆前後には、原爆投下があり、日航機墜落があり、終戦記念日がある。今年は戦後80年。改めて太平洋戦争について勉強したくなり、この本を読んだ。水木しげるなのは、直前まで妖怪ものの絵本を借りていたからである。 水木タッチのねずみ男絵柄ではなく、ごく普通のスケッチに本人の説明が加えられている。鬼太郎や貸本屋時代の作品以前に描かれたスケッチなので、後の時代にはない水木の絵の才能が現れている。普通の絵のようでいて、構図にせよタッチにせよ素人には描けない。 ラバウルはニューギニアの北、太平洋を望むビスマルク諸島にある。なぜあんなところに戦線を展開するのか今となっては疑問だが、声のデカい人間が主張すると誰も反論できなくなるのが日本の組織である。水木自身の体験した軍隊も、戦略とか装備以前に組織としての規律に欠けていた。 1ヶ月でも早く組織に入った者は後から入ったものを殴ってもよく、組織内の地位が上ならどんな理不尽な命令をしても構わない。読んでいて、80年経っても、戦争で散々な目に遭っても、日本人の心根は変わらないのだなあと改めて思った。 日本軍のメンタリティは、令和の広陵高校野球部やジャニーズの中居・国分の中に受け継がれている。芸能界は一般社会とは違うとしても、スポーツとか体育会は日本の組織全般に通じる。スポーツが腐っていれば社会もまた腐る。 戦争だから、各自が自由に行動するより上意下達で成果が上がるのは人類5万年の歴史から明らかである。とはいえ、下がバカでいいとはならない。指示どおり動けばいいなら動物でも機械でもいい。まして同じ階級で上下をつけたり、声のデカい人間・知性の劣る人間が支配する組織が長続きするはずもない。 私の働いた数ヶ所の職場も、多かれ少なかれそういう連中が牛耳っていた。1日でも早く入った者が偉い・階級が下なら奴隷と同じ・組織の発展より自分の利益と思っているから、私など合う訳がない。戦前の軍部が壊滅したように、日本の組織もいずれダメになるのだろう。 あるいは、日本人そのものが生き残れない宿命にあるのかもしれず、こういうメンタリティならそれも仕方ないと思う。組織が生き残るためには、能力ある人間が上にいなければならない。数を頼みに大声を出す人間が大勢を占めるようでは、その組織は長続きしない。いまの日本である。 下の人間は絶対服従・上の人間は一人いればいいという戦略は、毛沢東がすでに失敗している。習近平も危うく粛清されるところだったが、運よく生き残れた。今日、習政権が長期にわたるのは、同年代の才能ある人々が軒並み殺されてしまったのがひとつの要因である。 私も、必要に迫られて戦争しなければならない事態であれば戦場に行くのはやむを得ないと思う。しかし、訳の分からない能無しの指示で犬死にするのはまっぴら御免である。そういう時代でも場所でもなかったことに感謝しなければならない。 [Aug 18, 2025] 終戦記念日なので太平洋戦争についての本を読んでみた。旧日本軍は装備とか戦略以前に、軍隊としての規律が不足していたと思う。今日の広陵高校事件、中居・国分スキャンダルにもつながっている。 國友公司「ルポ 路上生活」
この種のルポ記事はいろいろな時代に書かれているが、この本は2020年代の実体験に基づく。2020年以降となると、私自身はすでにリタイアして通勤電車に乗ることもなく、新宿や上野に立ち寄ることもない。だから最近の様子はあまりよく分からないのだが、知らなかったことが多く書かれていた。 著者は1992年生まれだから、家の長男長女よりまだ若い。大学時代からライターを始め、「西成ルポ」などの著書がある。7年間かけて大学を卒業しフリーライターという、昔は結構見かけた経歴の書き手である。(YouTubeで顔出ししているが、ホームレスできるのかという風貌である) 2021年だからごく最近、ホームレス生活ルポのため新宿、上野、墨田川・荒川などの河川敷で数ヶ月を過ごした。最初の1日こそパンとジャムを買って食べたが、その後はホームレスの口コミで炊き出しに並んだり、観光バスで余った弁当などで過ごし、食費はほとんど使わなかったという。 まるで明治時代のお遍路のようだが、誰でもそういうノウハウが手に入る訳ではない。著者はコミュニケーション能力に優れており、近くにいるホームレスから巧みにその手の情報を入手するのだ。私のように対人スキルがないホームレスは、炊き出し場所も知らないし無料シャワーも知らない。 炊き出しをするボランティアや宗教団体の中には、講習会に来ると現金を配るところさえあるという。そうした善意に甘えることを割り切ってしまえば、食べるには困らないし少々の現金も得られる(大雨の時サウナに行ける)。ホームレスの本業のように考えられてる空き缶拾いは、体力を使うので勤勉な人がすることなのだ。 ホームレスなので住むのは路上や河川敷である。暑くても冷房はないしネズミやゴキブリ、害虫はそこらじゅうにいる。私にはとても無理だが、慣れてしまうとそんな場所でも熟睡できるらしい。著者も路面が堅く眠れなかったが、廃品のマットを手に入れて少し寝られるようになったという。 話は違うが終電専門YouTuberがすごいのは、ベンチで野宿すると蚊とか蟻だけでなく、ゴキブリや蝉などさまざまな害虫が来ることである。私にはとても真似できない。 ホームレスになったのはそれぞれ事情があるのだろうが、著者が気づいたのは社会生活にどうしてもなじめない者が多いことであった。「貧困ビジネス」にピンハネされることさえ許容すれば、アパートは借りられるし生活保護も受けられる。しかし、それに伴ういくつかのルールに耐えられないという人がホームレスに逆戻りするらしい。 そして、意外なことに年金受給者でありながらホームレスという人も多いらしい。定まった住所がないと所在証明(生存証明)がないので年金は受けられないと思いがちであるが、年金事務所に相談すればいろいろ方法があるらしい。そして、借家住まいで月5万ではとても暮らせないが、ホームレスで月5万あればかなり余裕ある生活ができるという。 そして、さすが日本と思わせるのは、住民票がなくてもコロナワクチン接種券はもらえるし(山谷で相談会がある)、台風が来れば避難情報が周知される。上に書いたように新宿区役所には無料シャワーがあるし、銭湯無料券もいただけるらしい。「健康で文化的な」とはいえなくても、生きていくことはできるのである。 この本を読みつつ思ったのは、やることがなくて退屈などというのは、贅沢の極みということであった。夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができて、食べるものがちゃんとあり、不快な物音や悪臭、不潔な環境に悩まされなくて済むことは、相当に恵まれているということである。 いまの時代であっても、ガザやウクライナにいたらできないし、日本であっても自然災害や原発事故に巻き込まれたらとたんにできなくなる。清潔な自分の家で、奥さんの作ってくれたご飯を食べられるのは、たいへん恵まれたことであることを改めて感じた。 チャールズ・サイフェ「異端の数 ゼロ」
著者は「エコノミスト」「サイエンティフィック・アメリカン」等で執筆するサイエンスライター。もちろんキリスト教徒なのだろうが、数学の発展に宗教がマイナスの影響を与えたことはきちんと指摘している。 「0」という概念はアラビア発祥ということは以前から知っていた。ヨーロッパ世界が「0」を知らなかったのは、指で数えられるのが1、2、3、…だからだというのは大きな間違いで、ギリシアの時代から0という概念そのものはあったというのが本書の指摘である。 ではなぜ、西暦1000年以降まで「0」なしできたのかというと(西暦0年はない)、0と無限は神(造物主)を冒涜する考えであるとして、異端とみなされたからである。キリスト教もそうだし、それ以前もそうだった。ピタゴラスやアリストテレスは0について思索する弟子を迫害した。 だから「0」がないのは、ルネッサンスに至るまで地動説を疑うことが許されず、いまだにアメリカの一部の学校で進化論を教えないのと同じことであった。ギリシア人はピタゴラスの定理を定規なしでどうやって見つけたかと思うが、定規の起点が何なのか考えると破門されたり殺されるのだから仕方がない。 それを考えるとギリシアの数学者は気の毒である。彼らは1より小さい数を分数で表わしたが、3分の1で早くも割り切れない。割り切れなければ無限に3が続く小数となるべきところ、3つに分割したうちの1つで思考停止したのである。「無限に続く」は異端だからである。 ピタゴラスの定理は本来、平方根を使わないと理解できないはずだが(直角二等辺三角形の長辺はルート2)、ここも思考停止した。無限に続く小数どころか、分数を使っても正確な長さは出ない。 虚数や超越数はともかく、数学を研究する上で循環小数、無理数といった概念を避けては通れないが、それは神を冒涜すると言われたらどうしようもない。真理を追究しようとすれば神(教会)に邪魔されるのは、ルネッサンスより千年以上前からそうだったのである。 いまや、「0」を使わなければ相対性理論も量子力学も説明できない。天文学も宇宙の理論も同様である。定規の起点が0でないといけないのは小学生にも分かる。しかし、西暦0年がないと理論的におかしいから0年を作ろうという人はいないし、アナログ時計のいちばん上が「12」であることを不思議だと思う人もあまりいない。 その意味では、キリスト教世界がここ二千年間において科学の最先端であったのは、よかったことばかりではないのかもしれない。 杉崎泰一郎「世界を揺るがした聖遺物」
聖遺物というと、キリストはじめ聖人ゆかりの品々という予備知識しかなかった。ところが、聖遺物は特にヨーロッパにおいてキリスト教の布教と密接に結びついていて、読んで目から鱗が落ちる思いだった。人生死ぬまで勉強である。 そもそも、ヨーロッパ諸国にとってキリストの活躍したイスラエル周辺は遠い。ローマからエルサレムまでの距離は約4,000km、日本・中国間よりずっと遠い。われわれには土地勘がないし、バチカンは聖ペテロの墓の上にあると言われるとそんなものかと思ってしまうが、中東で成立した宗教がローマ本拠というのは不自然なのである。(達磨の墓が日本にあるようなものだ) だから、キリストが聖書に書かれているように奇跡を起こし布教したとしても、それがそのままローマに来た訳ではない。ダ・ビンチが描いたようなヨーロッパ的な風貌ではなかったはずだし、言葉も通じない。キリストの時代から約400年経ってローマ帝国が国教化するまでの間に、かなり違った形に変質したのである。 わが国でも、お釈迦様が悟りを開いた仏教と、中国・朝鮮半島経由で入ってきた大乗仏教はまったく違う。さらに鎌倉仏教に至って、大乗仏教とも全然違う教えとなってしまった。同じような経緯・変質がキリスト教においても起こったのである。 ローマ帝国が侵略して領土に含めたいわゆるケルト人(ガリア人)の信仰が、中世以降のキリスト教には色濃く残っている。十字架に祈る、マリア像やキリスト像に祈るというのは、ほとんど偶像崇拝だと著者は指摘する。 イエス・キリストは偶像崇拝を禁じている。同じユダヤ教由来のイスラム教ではいまだにそうだから、バーミヤーンの石窟も破壊されてしまう。キリスト教は十字架に祈るのが当り前とわれわれは考えるが、実はそうではない。さらに、神様にお願いすることさえもキリストは禁じているのだ。 日本では、ご本尊(仏像)に祈る、ご神体(鏡・自然物)に祈ることにより、病魔退散、家内安全、心願成就を願う。だから外国も同じようなもので、拝む対象があちらの神様に代わるだけと考えるけれど、現世利益、諸願成就を祈ってはならないとキリストは言っている(少なくとも聖書にそう書いてある)。 現代でも、神父様が聖水やワイン・パンを使って信徒を清める。よく考えると、お祓いと変わらない。だから、日本人は信仰心がないとよく言われるが、キリスト教だって同じなのである。しかしこれは、ヨーロッパに入って変質したキリスト教がそうなのであって、もともとはイスラム教原理主義にも似た厳しい教えなのであった。 話は戻って聖遺物だが、もともとはキリストが磔(はりつけ)に遭った十字架とか、脇腹を差された槍とか、血をぬぐった布が聖遺物であった。しかし、時代とともにキリスト本人から使徒へ、さらに聖人とされる殉教した人達に対象が拡大した。十字軍が持ち帰った遺物がそれに加わる。 そもそも、木製の十字架や槍が千年も二千年も残るはずがない。とはいえ、実際にそれを旗印にして戦争に勝った、病気が治った、財を成したという事実が積み重なるものだから、真贋自体にそれほどの意味はない。キリストや使徒・聖人に関係あったかどうかよりも、どういう偉人がそれを旗印に戦争に勝ったか、財を成したかが重要なのである。 著者は中央大学文学部教授。西洋中世史で、特に教会・修道院が専門である。日本史の本だと自分だけが正しいといった書き方が多くて興ざめするが、この本はそういうことがない。よその国のことだから、研究者自身も自分が知るのはごく一部だと知っているからだろう。以来、西洋史や教会に関する勉強も少しずつしているところである。 あと、本筋にはあまり関係ないことだが、マドレーヌはもともと「マグダラのマリア」だったのは初めて知った。ヨーロッパ人は男も女も聖書からファーストネームをつけることが多く、みんなピーター(ペテロ)だったりポール(パウロ)だったり、マリー(マリア)だったりする。 マドレーヌもそのひとつで、ファーストネームがマドレーヌの料理人だかメイドが、貝殻で型をとった焼き菓子を巡礼者に供したことから世界的によく知られる洋菓子になった。もともとは「マグダラのマリア」という意味で、聖書にたびたび出てくる人物なのであった。 [Oct 29, 2025] 聖遺物というと最近ではゲームやアニメのアイテムだが、中世には重要な信仰の対象だった。キリスト教の布教経緯についても、参考となることが多く書かれている。 大村大次郎「宗教とお金の世界史」(爆)
何年かに一度、なんでこんなの読んじゃったかなあという本に当たる。図書館から借りたので身銭を切った訳ではないけれど、税金の一部が使われているというだけで釈然としない。そういう本は(爆)の表題で紹介している。過去にも何冊かあるので、もし興味ある方がいらっしゃったらバックナンバーをみていただければ。 この本のよくないのは、「世界史」を名乗ることである。「こぼれ話」程度にしてもらえばそういう本だと思うのだが、「世界史」というからには少なくともある程度の内容、歴史を通じた傾向や発展段階、裏付けとなる思想、地域間の伝播などを期待する。ところがそうではないのである。 キリスト教からイスラム教に改宗が相次いだのは、10分の1税で教会が強制的に募金を求めるのに、イスラム教はそんなことをしなかったからだというのが著者の主張である。 確かに、税金が安い方になびくのはありがちなことで、改宗のきっかけの一つであったことはあるかもしれない。しかし、それだけの理由なんてことがあるのだろうか。 みんながみんな命が大事おカネが大事で改宗するなら、江戸幕府はなぜあんなにキリシタン相手に苦労したのか。日本人が宗教心が篤くて諸外国が薄いからなのか。むしろ逆ではないのか。心のよりどころを金銭的有利不利で切り替えるような人はそれほど多くないはずだ。 スペインやポルトガルの世界進出も、キリスト教の布教とカネ勘定が結びついたものと著者は言う。そういう目的で動いた人が含まれていたことは否定しないが、キリスト教を広めたい、将来は天国に行きたいと思う人はそんなに少なかったのか。布教する中で殺された人が決して少なくないというのに。 結局のところ、渡る世間はカネ次第。みんな損得で動くというのが著者の言いたいことだが、お釈迦様にせよイエス・キリストにせよ、そんな小さい意図で教えを立てたとは到底思えない。理想や信念だけで他人は動かないが、カネだけでも動かない。当り前のことである。 Wikipediaによると、著者はペンネームで本名不詳だそうである。本名が分からないから、本当に国税庁で働いていたかどうか確認できない。もし本当だとしても、10年程度の経験で国税の奥義は分からないだろう。私も10年銀行員をやったけれど、銀行業務の奥義なんてとても分からない。 著者が税金のプロを名乗るなら、私だって金融のプロを名乗ってもおかしくないけれど、恥ずかしくてとてもそんなことはできない。ところが著者は税金に関する著書を何十冊も書いている。よっぽど恥を知らないのか、実は個人ではなくプロダクションなのだろうか。組織であれば恥ずかしいとは思わない。 [Nov 20, 2025] キリスト教に関して最近調べた中で読んだが、はっきり言って「世界史」ではない。また、著者は税務署に10年いただけで「国税庁OB」を名乗っているが、10年くらいでOB面されては国税も迷惑だろう。 桃崎有一郎「中世武士団偽りの血脈」
副題「名字と系図に秘められた企て」だが、中世武士団が藤原一族や源氏・平氏を僭称することに何か秘密の意図があったと述べている訳ではない。その意味では、読んでいて目から鱗が落ちるということはない。 確かに著者は中世の古文書をよく調べていて、どういう名乗りを誰がしたということは参考になる。また、よく言われる近藤は「近江の藤原」で、佐藤は「左衛門尉の藤原」ではなく、父系と母系の双方から一字ずつ取って「二姓合成通称」としたのが始まりというのも、確かにそう名乗った武士もいたかもしれない。 しかし、みんながそうとは考えにくい。父系が佐伯氏で母系が藤原氏、だから本来藤原ではないのだが、通称佐藤で藤原一族を装うことはあったかもしれない。しかし、武士のステータスは血筋でなく実力。弁慶は武芸と腕力に優れていたから義経の郎党筆頭なのである。 そして、時代が下って戦国時代、織田信長の通称は上総介である。別に房総半島に地盤があった訳ではなく、上総国府の二等官に任命された訳でもない。武士としてふさわしい名前と思ったからそう名乗ったのである。大岡越前も越前を治めていないし、吉良上野介も上州に領地はない。 地方の行政官だけでなく、朝廷の役職を使うことも多かった。浅野内匠頭は内匠寮の長官だし、主膳、式部、掃部(かもん)もよく使われた。今日でいうと経済産業省や国土交通省、文部科学省、宮内庁の役職だから、あまり強そうでない。 「秘められた企て」と副題を付ける以上、なぜ武士達はそうした名乗り、通称名を名乗るのがふさわしいと思ったのか考察するのかと思ったが、残念ながらそういうことはない。昔のボクサーのリングネームと同じで、強そうだから使ったというだけである。 もうひとつ不満なのは、貴姓を詐称したとされる時期が、前九年後三年の役だったり、院政期だったり、あるいは鎌倉・室町時代と時期的にかなり離れていることである。 平安時代も終わりに近づくと、殿上人はほとんど藤原氏なので、摂関家であっても一条、九条、近衛など通称を名乗らないと区別がつかなくなった。その時期の「△藤」と、前後五百年間近く違う時期とは、事情が違うように思える。 鎌倉・室町期になると平安時代ははるか昔である。「わが家の先祖は誰々」という伝承はあっただろうが、それを自分達のアイデンティティと結びつける発想まであったかどうか。それよりも「四代前の祖先が近江介だから近藤」の方が自然に感じる。 私自身、親から聞いているのは四、五代前までのことくらいで、それより前はどうしていたのか知らない。五百年違えば十四、五代。そんな祖先のことを知らないのは、私が貧乏人だからという訳でもあるまい。 思うに、系図だとか家伝が残っているのは貴族などごく一握りの家系だけで、大部分の家族は紙に書かれた記録など持っていない。父系と母系との違いも、記録に残すから名字は父系となるので、記録がなければ先祖は藤原氏というだけである。父系か母系かにこだわって伝承されたとも思えない。 だから、著者の主張する「二姓合成通称」についても、それを通称名にした武士もいたし、そうでない武士もいたということだろう。 「佐藤」が佐伯氏と藤原氏の合成までは納得できても、「後藤」がもともと五藤で五百木部(いおきべ)氏というのはちょっと苦しいようだ。秘められた企てでもないし、偽りの血脈ということもできないと思う。 [Dec 17, 2025] 副題「名字と系図に秘められた企て」だが、中世の武士達が藤原一族を装うことで何かを企てたと述べている訳ではない。いわゆるアイデンティティの確立であり、織田信長が通称「上総介」なのと同じことのように思う。
イーバン「Bottle of Lies」
アスクウィズ「80歳、まだ走れる」
水木しげる「ラバウル戦記」
國友公司「ルポ 路上生活」
サイフェ「異端の数 ゼロ」
杉崎泰一郎「世界を揺るがした聖遺物」
大村大次郎「宗教とお金の世界史」(爆)
桃崎有一郎「中世武士団偽りの血脈」