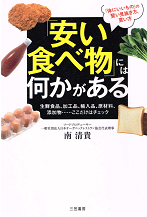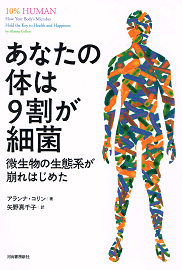更科功「美しい生物学講義」
スティーヴンス「誰もが嘘をついている」 更科功「美しい生物学講義」
さいきん一押しのダイヤモンド社の本である。今回は翻訳書でなく日本語で書かれた本だが、養老孟司先生や佐藤優が推薦しているだけあって、読み応えがある。 セス・スティーヴンス「誰もが嘘をついている」
図書館で背表紙をみた時、ビッグデータを頼り過ぎると間違えるという「統計のウソ」的な本かと思った。読み進めると内容はまったく逆で、ビッグデータは嘘をつかない、人間がアンケートで答える内容が嘘ばっかりだというものである。 野村朋弘「諡(おくりな)」
まず、私の不勉強についてお詫びしなければならない。しばらく前の記事で、醍醐天皇はチーズケーキ(醍醐)が好きだから諡号となったと書いたが、これは間違いで、醍醐は「追号」であって「諡号」ではない。 モントゴメリー&ピクレー「土と内臓」 原題「Hidden Half of Nature」、自然の隠れた半分である。自然というと、動物や植物といった目立つものばかり見てしまうが、それらよりはるかに広大な微生物の世界があるという趣旨である。「土と内臓」は、その世界を意味する超訳である。 森達也「オカルト」
オカルト系については、学生の頃たいへんホットな話題だった。こっくりさんとかユリ・ゲラー、ノストラダムスのブームがあった。オウムの幹部連中も私とほとんど同年代だし、この本の著者もひとつ違いである。 南清貴「安い食べ物には何かがある」 物価高の折柄、食料品の値段もうなぎ登りである。役所と政治家が一体となって消費者物価の伸びを低く操作しているから、年金は増えないのにインフレがどんどん進む。できるだけ安い買い物をしたいのは人情である。 藤田一照・伊藤比呂美「禅の教室」 お盆だからという訳ではないが、仏教について。そもそも葬式や法事は仏教とあまり関係ないと思っているけれど、この本の著者もそう考えているようである。 藤田一照師は曹洞宗の僧侶であるが、寺の二代目ではなく宗派の本部にいる訳でもない。長年、米マサチューセッツ州で、禅の普及活動に携わってきた人物である。 曹洞宗の禅堂だから永平寺や総持寺から経費が出てやっていると思いがちだが、そうではない。いろいろアルバイトをして生活費を工面し、禅に興味をもったアメリカの人達と、勉強会のような形で普及活動を行ってきたという。 もともと禅や仏教になじみのないアメリカの人達に教えてきたから、一照師の教えはわかりやすいし納得できる。禅はテクニックではなくポエットであるというのもその一つで、結跏趺坐とか半眼とか公案とかは禅の本質ではないという。 ところが実際には、ほぼすべての禅寺は「形」から入るから、テクニック重視になる。入山作法から一日の生活から座禅まで、実はそれぞれ意味があるにもかかわらず、まず「形」である。昔からそうやってきた、うちの寺ではこうしているといってやり方を押し付けるのが普通である。 そういう話を聞くと、わが国仏教低迷の理由の一端が分かったように思う。一言でいうと、寺が体育会系になっているのである。先輩の言うことは絶対、頭で考えず体で覚えろ、嫌ならやめろ。すべて体育会系の発想である。 ただ、禅宗の場合でいうと、曹洞宗を始めた道元からして体育会系の考え方である。だから道元自身に弟子は数人しかいないし、後援者がいたので永平寺はできたものの全国に信徒がいた訳でもない。 著者の一照師はアメリカ人にも分からせなければならないという必要性があるから、素人にも分かりやすく説明するけれども、道元は出家者だけ、男だけ、自分に付いて来られる者だけ分かればいいと思うから、正法眼蔵は分かりにくいのだ。 お釈迦様が仏教を始めたのは、現世の四苦八苦から逃れるためにどうしたらいいかと思ったからで、それはきわめて個人的属人的動機である。 そのひとつの答えが、本書でも触れられている「貧乏を苦にするのは自分の頭が貧乏を作り出すからである」ということであろう。頭(脳)が苦しいと思っていることがすべて、体も苦しい訳ではない。 体が苦しいと思うのは水の中で呼吸ができなかったり、狭い場所に大勢詰め込まれて新鮮な空気がないことであり、それが本来の苦しさである。貧乏も自分が認められないことも、空気がないのと違って生きるのに直接の影響はない。 私も、これまで生きてきたよりずっと短い期間しか生きることはない。頭の中で作り出した幻想のために苦しむことがあるとすれば、それは避けられる苦しみであろう。少なくとも、寒かったり狭かったり、腹が減ったりして苦しいことは、いまの世の中ほとんどない。 対談相手の吉田さんが「仏教の本ってなぜ仲間内の言葉ばかり使って、自分達だけ分かろうとするんだろう」と疑問を持っているので、一照禅師も誤解を恐れず分かりやすく説明しています。なぜいま仏教に元気がないかヒントになる本でした。 アランナ・コリン「あなたの体は9割が細菌」
以前書評で採り上げた「土と内臓」は、土と同様に内臓も微生物が住める環境とすることが望ましいという内容だったが、この本はさらに過激である。人間の遺伝子が体内において占める比率は10分の1であり、残り90%は微生物の遺伝子で、それが人間のさまざまな調節機能をつかさどっているという。 2015年刊行で、原題は"10% Human"。いままでの認識では、われわれの体内においてさまざまな調節を行っているのは人間の遺伝子に基づく情報であり、具体的には自律神経やホルモン、血液や免疫系の働きによって生活していると思われてきた。ところが実際は、人間の遺伝子(ゲノム)だけではできないらしいのである。 微生物ということでよく例にあげられるのが牛である。牛は基本的に草食で、牧場や草原に生えている草を食べてあれだけの体を維持している。ところが、牛自体に草を消化する機能はない。それを行っているのは微生物で、牛の消化器に住み着いた彼らが草を消化して牛に栄養素を供給しているのである。 人間も、ヒトの遺伝子として栄養吸収を行っているのは小腸までで、大腸には消化吸収の機能はほとんどない。だからかつては、大腸など不必要と考える専門家が多くいたし、盲腸など進化の過程でいらなくなった機能が残っているだけとわれわれは習った。ところが、大腸も盲腸も、微生物の住処として、たいへん重要な役割を果たしているらしい。 致死性の伝染病がほとんど姿を消した現在、人類の健康上最も大きな脅威となっているのは「二十一世紀病」といわれる諸疾患である。肥満や糖尿病、花粉症から関節リウマチまで幅広くある免疫疾患、自閉症などの精神疾患。それらは感染症が少なくなったから目立つだけでなく、先進国といわれる国々において統計的に有意に増えている。 感染症・伝染病には病原菌やウイルスといった原因があったが、お互いにあまり関係なさそうにみえる「二十一世紀病」に共通の原因はあるのか。それを調べるうちに、どうやら腸内環境の変化によって住み着いている微生物の構成が変わり、本来必要とされる機能が果たされなくなった可能性が大きいことが分かった。 花粉症が大流行した際、これは人間の体内に寄生虫がいなくなったことが原因だとして、わざわざサナダムシを体内で飼った医師がいたが、そんな大きいものでなく微生物だった訳である。花粉症くらいなら対症療法が可能だが、アトピー性皮膚炎なら、膠原病ならどうか、自閉症はと考えると、対症療法では限界があることが分かる。 人間の場合は無菌室で育てることができないから実験できないけれど、マウスはそれができて、腸内にまったく微生物がいない無菌マウスを作ることができる。無菌マウスにある微生物を植え付けるとそのマウスは必ず太るし、ある微生物では必ず痩せる。食生活も体内の代謝もマウスの遺伝子ではなく微生物が操作しているらしい。 そして 「二十一世紀病」の発端を調べると、どうやら第二次大戦直後がそのタイミングで、米国において肥満人口が急激に増えだしたのはその時代からである。肥満というと食べ過ぎとかジャンクフードに原因を求めることが多いが、どうやらそれだけではなく、腸内微生物の構成が変わったのがその時期らしいのである。 著者は、大きな原因が抗生物質の乱用にあるのではないかと考察している。抗生物質により多くの感染症が絶滅したけれども、本来は必要ない人にも抗生物質を処方する例が増えた。 たとえばウィルスには抗生物質は効かないが、ほとんどの医師はウィルス疾患に抗生物質を処方する。食肉用の家畜や養殖魚にも抗生物質は与えられているので、避けようとしても避けられない。 いまや 「二十一世紀病」は先進国だけでなく、発展途上国のいくつかに拡大している。これは、食糧事情の向上、衛生環境の改善が、むしろそうした疾患を増やすことになっている可能性がある。 世の中がそう動いている以上避けられないことだとしても、手の打ちようがなくなるまでにできることはないのか。すでに先進国では、健康人の腸内物質を移植するところまで来ているらしいが、それは難しくても、微生物が腸に住みやすくなるよう土壌を整えること。規則正しい生活(日光)、運動(土地を耕す)、食生活の改善(肥料)は有効なようである。 [Aug 30, 2024] 腸内微生物が人間に及ぼしている役割は小さくなく、二十一世紀病と呼ばれるアレルギー等の免疫疾患や自閉症などの精神疾患も、微生物の組成が変わったことが原因と考えられるという。 牧田善二「医者が教える食事術」
ちょっと前までキワモノ扱いされていた糖質制限だが、いまや糖尿病のメイン対策のひとつとして確立している。江部先生だけでなく、最近は牧田先生が精力的に情報発信されている。 牧田先生は米ロックフェラー大学で研究された糖尿病専門医で、AGE(終末糖化産物)の研究者であった。近年は銀座にクリニックを開院し、自費診療(!!)で進行した糖尿病患者の治療に携わっている。 江部先生の高雄病院でもその当時糖質制限食は保険がきかなかったので、健保対象でないから金持ち相手だと決めつけることはできない。大多数の開業医や薬品会社に都合が悪いから、意地悪されて対象から外されている可能性もある。 牧田先生自身も大学病院にいた時には、血清クレアチニンが悪くなってから腎臓専門医に紹介状を書いていたという。ところがある時、専門医から「クレアチニンが悪くなってからでは手遅れですよ。尿アルブミンを診て、まだ手が打てる時に紹介してくれないと」と言われたそうである。 これを機会に一念発起した先生は、外国の論文を欠かさずチェックし、糖尿病の最大の合併症である腎臓病について勉強し直したそうである。こうした自身の経験もあって、勉強不足の医者に任せていたら直せるものも直せない。手遅れになってから言われるだけだと警鐘を鳴らしている。 江部先生の時代と違って、糖質制限に意味があるかないかの議論は必要がなく、糖質制限は有効というところからスタートする。そして、糖質が何g含まれるかよりも、血糖値をどれだけ上げるかがもっと重要であるという。いまは、フリースタイルリブレという計測器で、リアルタイムに血糖値が計測できるからである。 これはいわゆるGI値の話だが、先生にはこだわりがあってGIという言葉は使わない。ともかく、すぐ腸に届いて血糖値を上げる清涼飲料やお菓子、単体で摂取する炭水化物をまず避けろとおっしゃる。それを知るためには、フリースタイルリブレはたいへん効果的ということである。 先生の治療の主眼は、ともかく人工透析にしないことである。腎臓の濾過機能はダメになってから回復させることはできず、人工透析か腎臓移植しか方法はない。だから、全面的にダメになる前に治療を開始し、回復しないまでも進行を止めることが重要だという。 具体的には、検診や内科医の検査で指摘される尿たんぱくとか血清クレアチニンが異常値となってしまえば手遅れで、そうなる前に手を打たなければならない。それには尿アルブミンの検査が欠かせないし、どういう処方で進行を食い止められるかの知識が必須だが、残念ながら多くの内科医にその知識がないのが実態という。 今回、私自身の経験として、いきなり腎臓が悪いと言われSGLT2阻害薬を処方されたのだが、検査数値(尿アルブミンを含む)に異常はないし、腎臓という見立てには疑問をもっている。それでいろいろ調べた中に牧田先生のこの本もあって、糖尿病と腎臓病について言えば、私の考えはそう外れていないように思える。 とはいえ、いくつか物足りない点もあって、いきなり牧田クリニックの投薬の説明に入ってしまうのは商売柄やむを得ないとしても、まず生活指導なり薬に頼らない方法を説明していただければもっとありがたい。 その意味では、血糖値の管理、糖質中毒の回避に重点が置かれ過ぎていて、塩分制限やたんぱく質の制限にはあまり熱心でない(もちろん腎臓の話の中で触れられてはいるが)。糖尿病の進行が腎臓に悪影響があるのは言うまでもないが、塩分・たんぱく質の過剰摂取も負けないくらい悪影響がある。 もう一つ、人工甘味料や合成添加物がよくないのは分かるけれども、じゃあ糖やアルコールと比べてどちらがよくないんですかという説明がない。個人的に、ビールとノンアルコールビールのどちらがどれだけ悪いのかにたいへん関心があるので、そこの説明がないのがやや不満である。 ただ、人工甘味料や合成添加物の害についてはまだまだ研究が進んでいないというのが実態だし、アルコールは少量でもやっぱりいかんというのはつい最近の研究結果である。この分野は日進月歩だから、すべての分野で最先端という訳にはいかないかもしれない。 [Sep 27, 2024] 江部先生はパイオニアだから、そもそも糖質制限とは何かから話を始めなければならなかった。牧田先生は糖尿病と腎臓が専門で、糖質制限は当然というところからスタートする。 山田悟「ロカボで食べるとやせていく」(爆
数年前から糖質制限を実践中で、ブログにもその経過を逐次記録している。だから糖質制限に関する本は好意的にみてきたのだけれど、これは例外である。こういう本・こういう著者が前面に出てくると、糖質制限の信頼性そのものが損なわれるように思う。 著者の肩書は、北里研究所病院糖尿病センター長である。新千円札に採用された明治時代の名医・研究者の創設した病院である。にもかかわらずこうした内容を書くというのは、想像力がないか自分で書いていないかのどちらかだろう。 本全体に「ロカボ」という新語(登録商標?)の宣伝臭がぷんぷんするのは置くとして、この人は本当に医師免許を持っているのかと思うくらい医学的な常識がなく、そのことを自慢げに主張するあたりは正常な神経とも思えない。 例えばこのセンセイ、糖質制限に出会うまではカロリー制限一本だったそうである。それは日本中の大半の医者がそうだったし、カロリー制限がダイエットや糖尿病の治療に役立つことは確かなので、そこまではいい。(カロリー制限の問題は、長続きしないことと、糖質制限に比べて効果が薄いことである) その文脈で、血液検査で中性脂肪の多い患者には脂肪制限も奨めていたと書いてある(この著者の本を何冊か読んだので、「ロカボで」の本ではないかもしれない)。脂肪制限もまあ許すとして、「先生、私、脂肪なんてほとんど摂ってないです」という患者に、「だったら中性脂肪増える訳ないでしょう」と言ったという。 こんなことを北里病院の糖尿病センターで言ったとすれば、本当に医師ですかということである。私が消化について勉強したのは60年も前だが、その時から脂肪は消化されると脂肪酸とグリセリンになると書いてあった。脂肪酸が中性脂肪にならない訳ではないが、それには遠い道のりがある。 中性脂肪は生物の体内に蓄えられた脂肪で、元になるのは炭水化物であり糖質である。食べた脂肪がそのまま中性脂肪になるなら、草食動物はどうやって脂肪ができるのか。それを言っているのが素人なら仕方ないが、有名病院の医師がそれで患者を診ているというから驚きである。 そのことは、糖質制限が知られるようになって新たに判明したことではない。それこそ何十年前から、医学・薬学・栄養学とか以前に、小学校の理科で勉強することなのである。それを知らないし、知らないことを恥ずかしげもなく本に書いてしまうのは本当に恐ろしい。 もうひとつあきれるのは、カロリーなど気にせず腹いっぱいになるまで食べろというのである。確かにカロリー信仰にはあまり意味がないが、かといって腹いっぱい食べて健康にいいはずがない。 これには注釈があって、満腹中枢に異常がある人は腹いっぱいになっても満腹感がないので、そんなになるまで食べないでくれという。だったら、日本人の大多数は満腹中枢が異常である。腹いっぱいと満腹感にタイムラグがあるのは当り前で、普通の医師(人)は腹いっぱい食べろなんて言わない。 だから普通は、満腹感が感じられるようゆっくり食べましょうと指導する。腹八分目とゆっくり食べることは、ずっと昔から健康管理の基本である。糖質以外なら腹いっぱい食べていいなどというのは、ただの受け狙いであろう。 他にも、たんぱく質も塩も糖質でないから、いくら食べてもいいなどという書き方をするけれども、どういうものであっても食べ過ぎは体に毒である。人工甘味料はただの水よりダイエット効果があるという説に至っては、トンデモ論としか言いようがない。これが糖質制限なら、なるほど糖質制限は長年無視されてきただけのことはある。 製薬会社や多くの開業医に不利になるからといって、理論上の裏付けも効果も実証されている糖質制限を無視し続けることと、糖質制限が儲かりそうだといって、ロカボだ何だと商売を始めることは、同じことの違う側面である。繰り返しになるが、この本はトンデモ本である。 [Nov 26, 2024] 糖質制限が糖尿病の治療に有力であることは自分の経験から分かるけれども、この本・著者はどうかと思う。 石原比伊呂「北朝の天皇」
久しぶりに歴史の本を読んでいる。古代史や戦国史はそれぞれ思い入れが激しく、自分が正しく他人は間違っているという傾向があるのであまり読みたくない。近頃続けて読んでいるのは、鎌倉時代から室町前半にかけてである。 南北朝は戦前の天皇史観の時代にたいへん盛り上がった。筑波山系にもその時代の山城・難台山城があって、南朝に属した武士の顕彰碑があったりする。大河ドラマになることもないし、ほとんどの人にとって関心のない時代だが、史料が豊富な割に深く研究されることが少ない。 この本の著者は聖心女子大准教授で、室町時代が専門である。専門というと蛸壺的になってしまうことがしばしばだが、この著者はかなり分かりやすい。例の挙げ方が少々受け狙いと感じるけれども、多くの人に理解してもらおうという姿勢の表われと前向きに評価したい。 例えば鎌倉から室町時代に頻発した徳政令。教科書的には御家人救済とか寺社の圧力とか、一揆への発展といった文脈で説明されているが、そもそもこの時代、幕府は全国を治めている意識などなく、あくまで御家人を対象としたものだったという指摘は目からウロコであった。 徳政令を出しても御家人以外の債務を免除したつもりなどないし、それは朝廷の守備範囲と思っていたという。 われわれは、徳川幕府が寺社や貴族にも諸法度を作って統制したことを知っているので、それ以前の幕府もそうだと思ってしまうがそれは違うらしい。鎌倉幕府・室町幕府は武士でさえすべて統制していた訳ではなく、統制していない武士が「悪党」と呼ばれるのである。 よく考えるとそれはそうで、「幕府」の意味は前線基地ということだから、そのルールは兵士を統制するためのものである。例えば自衛隊のルールが一般社会に適用されるということになると、われわれも困るが自衛隊だって戸惑うだろう。 徳川幕府がそれをやったのは、室町幕府の統制が甘すぎて戦国時代になってしまったことへの反省というか対応であり、それを受け継いだのが第二次大戦前の軍部という訳である。 だから、北朝は室町幕府が傀儡として作ったという見方は、事実の半面しか見ていない。幕府が直轄する武士を除く寺社や一般人、幕府統制外の武装勢力に対するルールは、朝廷が定めるのが当時の認識だったのである。 中でも大きいのは裁判、土地をめぐる紛争の解決である。だから、建武の新政で南朝が全国を支配した際、土地所有権をめぐる紛争でみんな京都に押し寄せたのである。二条河原落書にいう「本領ハナルヽ訴訟人 文書(もんじょ)入タル細葛(ほそつづら)」である。 これは、後醍醐天皇が全部自分で決めると言ったからそうなったのだが、伝統的に、持明院統(のちの北朝)は慣習とか手続き面を重視する朝廷であったのに対し、大覚寺統(のちの南朝)はトップがすべて裁断する傾向があったからという。北朝はただ室町幕府の指示に従って動いていた訳ではないのである。 そして北朝も、観応の擾乱(正平一統)で光厳・光明上皇、崇光天皇と皇太子が南朝に幽閉された影響で、崇光系(伏見宮)と後光厳系に分裂し、後光厳系が皇位を継承することになる。そして、南北朝合一後に後光厳系の血筋が絶えて再び崇光系に戻り今日に至っている。 室町幕府の将軍の中でも個性が際立っている足利義満と足利義教が、この崇光系と後光厳系の確執に深く関わっていて、そこには皇位継承だけでなく皇室が持つ荘園の相続や、有力寺社の門跡の権利などが絡んで、いろいろ大変だったようである。そのあたりを知ると、室町時代の面白さがよく分かる。 [Dec 18, 2024] 南北朝時代は、戦前の天皇史観から南朝が正統とか楠木正成は忠臣という観点が強調されるが、幕府も朝廷も武士も貴族も、もっとしたたかであった。
野村朋弘「諡(おくりな)」
モントゴメリー&ピクレー「土と内臓」
森達也「オカルト」
南清貴「安い食べ物には何かがある」
藤田一照・伊藤比呂美「禅の教室」
コリン「体は9割が細菌」
森達也「オカルト」
南清貴「安い食べ物には何かがある」
石原比伊呂「北朝の天皇」
前回採り上げたヘンリー・ジーの「生物全史」が人間中心、もっとも高度に進化したのが人類という考え方で構成されているのに対し、この本は何が高等で何が下等かなんて決められないし、意味がないという。そのとおりだと思う。
さて、題名からすると生物学全般について概説している本のように思えるが、実際は科学全体の議論から始まって、生物学については部分的に扱っているだけである。科学全体の話は面白くない。そして、生物の定義もあまりすっきりしない。
少なくとも地球上の生物については、①膜で外部と区切られていること、⓶代謝すること、③自分の複製を作ること、で定義されるというが、本の後半では、限りなく長く生きれば複製は作らないかもしれないと保留している。
とはいえ、生物学についての最近の知見はいくつか含まれている。印象深かったのは、人類と類人猿を分けたのは、一夫一婦制かもしれないという仮説である。
人類と類人猿の体の違いは、直立二足歩行と犬歯の縮小である。二足歩行はニワトリやティラノサウルスだってするけれども、直立するのは人類だけである。類人猿も二足歩行できるけれど、基本的に四足歩行で全速で逃げる時はそうする。
犬歯の縮小は道具を使って狩りができるようになった結果といわれてきたが、道具ができるより前に犬歯は小さくなっていたらしい。そのことと直立二足歩行を両方説明できるのは、人類は最初から一夫一婦制だったのではないかという仮説だという。
一夫一婦制によりオス間の闘争が少なくなったことにより、犬歯は小さくなった。また、家族に食糧を持ち帰る必要から両手を空けるため、直立二足歩行の必要が生じた。
牙でライバルを噛み殺したり、手足とも使って速く走れる個体よりも、争いを好まず、家族を飢えさせない個体の方が子孫を多く残せる、つまり進化上有利な戦略であることから、人類はいまのようになったというのが最新の仮説である。
半世紀前の社会学では、家族制度の発展形態として、原始乱婚制からプナルア婚、女系家族、男系家族なんてことを教わってきたけれども、実は最初から一夫一婦制で、それにより人類が類人猿から分かれたという見方が有力になっているのである。
私の若い頃すべての学問でマルクス的な考え方が幅をきかせていて、社会も未開の時代から徐々に発展すると教わってきたが、理屈で家族を作る訳ではない。原始時代が乱婚制で、知恵がついたら一夫一婦制というのは考えてみれば不自然である。
アラブの石油王だって昔の天皇だって、奥さんが複数いるくらいでみんながオットセイのようにハーレムを作っている訳ではない。資源を得るのが難しいほど、オスが子育てに協力した方が生き残りやすいはずである。
カルフーンのネズミ実験によれば、ハーレムを作るオスの他は大部分がメスを得られないという社会では、家族制度は次第に崩壊し、最終的に生殖活動が行われなくなるという。
鳥だって動物だってつがいになるものは多くいるし、オットセイが繁栄しているかというと、衰退ないし絶滅に向かっているというのが実態である。家族制度は理屈ではなく、どういうやり方が生き残りに有利かなのである。
[Jan 24, 2024]
どちらかというと科学全般の説明が多く、かったるい印象がある。いくつか採り上げられた生物学の話題の中で、人類の家族制度についての仮説が興味深かった。
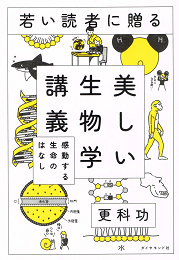
競馬ファンにとって印象深いのは、アメリカンファラオについての考察である。この馬はアファームド以来37年ぶりの米国三冠馬というよりも、馬名登録の際にスペルを間違えたことで有名なのだが(ファラオpharaohとあるべきところpharoahで登録した)、コンサルタントがセリの時点で素質馬であることを見抜いたそうである。
その根拠が、昔ながらのホースマンのように血統とか馬体とか歩様ではなく、統計データに拠ってなのである。特に注目したのが左心室の大きさだという。(米国では、簡単に馬の超音波検査ができるのだろうか)
人間に話を移すと、プロスポーツの花形選手、特にアフリカ系(黒人)選手には貧困層からスターダムに登りつめたというアメリカンドリーム的イメージがある。しかし、ビッグデータでみるとそれは正しくないという。
MBAやNFLのトップ選手の中には確かに貧困層出身者もいるが、マスコミ報道で目立つだけで、比率としては必ずしも大きくない。母集団の数とトップ選手を比較すると、むしろ裕福な育ちの方がプロになりやすく、トップ選手にも多いのだ。
それは、各選手が自発的に明らかにしている出身地や出身校のプロフィールから解析できる。この説明で面白かったのは、貧困層やシングルマザーにはポビュラーネームより「キラキラネーム」を子供に名付ける例が多いという指摘である。
確かにNFLのトップ選手でも、「パトリック」マホームズをはじめ(彼は父がMLBで母親が白人だから別格かもしれない)、ラッセル、ラマーなど普通のファーストネームがほとんどである。キラキラネームを探す方が難しい。
競走馬やプロスポーツ選手は従来型のデータで、技術的進歩やデジタル化によって検索が容易になっただけだが、ビッグデータの破壊力はまた別である。いま現在、もっとも多くのビッグデータを持つのはGoogleである。
例えば、利用者がどんな検索ワードを入力しているか、リアルタイムかつ網羅的に把握できるのはGoogleだけである。ビッグデータのどこが優れているというと、類型別の条件づけをしてもデータの精密性が変わらないからである。
デジタル写真で、画素数が少ないものと多いものを著者は例として挙げる。画素数が少ないものを拡大すると画面は粗くなるが、十分に多ければ画像は劣化しない。
地域ごとや年齢ごと、その他諸々にカテゴリーを分けても、十分なデータが確保できるのがビッグデータである。
題名の印象とは異なり、ビッグデータは嘘をつかないという本である。ビッグデータが社会科学を真に科学たらしめることになると著者は主張する。
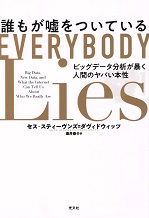
それでは、ビッグデータは万能なのか?例えば翌日の証券市場を予期できるかというと、それはできないと著者はいう。
100枚のコインを毎日投げて、証券市場の騰落と一致するものがある可能性はきわめて少ない。しかし、100枚を1万枚、10万枚と増やしていけば、値上がりする日に必ず表、値下がりする日に必ず裏となるコインも出てくる。
しかし、そのコインを投げて表になったから翌日は値上がりするかというと、そうなるとは限らない。前日までの的中はあくまで偶然だからである。限りなく多くサンプルをとれば偶然の一致が起こる可能性も高まるが、次も当たる確率はあくまで偶然だからである。
同様に、数限りなくある遺伝子のどれかが成績優秀者に共通するからといって、その遺伝子が天才遺伝子であるかどうかは分からない。偶然そういう結果であった可能性を排除できないからである。
ビッグデータを使った解析では、関係性は推定できるけれど因果関係であるかどうか分からない。初めに紹介した馬の能力の話でも、心臓(左心室)が大きいことがなぜ競争能力を高めるのかは分からない。原因と結果ではないのかもしれない。
とはいえ、そこまで分からなくても有効な意思決定ができるならば、それで十分ともいえる。いくつか紹介されていた事例の中で興味深かったのは、貧乏人が長生きするためにもっとも有効な手段は、カネ持ちの多い地域に住むことだそうである。
著者は、意識せずにカネ持ちの生活習慣と似てくるからと説明しているが、禁煙や運動習慣や規則正しい生活を真似するだろうか。おそらくこれは、そういう人達はそういう地域を好むという原因と結果の逆転があるような気がする。
正直言って、内容はともかく書きっぷりが小生意気で鼻に付く。翻訳者が原著のトーンを日本っぽく通訳したのだと思うけれど、せっかくの主張が薄っぺらに感じられるのは惜しまれる。
「Everybody Lies」という題名にしても、内容を適確に表してはいない。おそらく、本書中でも触れられている「ネット上のA/Bテスト」で、もっともクリックする人が多かった、つまり人目を引く題名であったからこうしたのだと思う。
読者に新たな知見に触れてもらいたいと思っていたら、こういう題名は付けないだろう。このあたりからも、著者の性格は推測できるが、「俺は頭がいい」と言いたいから本を書くのがアメリカ的なのかもしれない。
[Mar 7, 2024]
平安時代の貴族は諡号と追号を厳密に区別していて、それぞれの手続きがまず違う。そして、諡号が価値判断、さきの天皇の業績や人柄を評価して定めるのに対し、追号は価値判断を含まず、いわば通称である。
「醍醐」は諡号でなく追号で、御陵のある地名から採った。このあたりの地名・醍醐山は醍醐天皇が生まれる前からその名前である。おそらくチーズケーキを醍醐と名付けたのも、地元の地名から採用したのだろう。いまでもよくある話である。
そして、私は過去数十年来、井沢元彦はすごいと思ってきたのだけれど、これについても疑問符を付けざるを得ない。というのは、彼の十八番ともいえる怨霊信仰の決め手の一つが、「贈・徳の字鎮魂法」だが、これは井沢元彦のオリジナルではなく、平安時代すでに貴族が書き残していることだったのである。
「贈・徳の字鎮魂法」は、聖徳太子からはじまって、孝徳、文徳、崇徳、安徳、順徳、顕徳(後鳥羽)の徳の字が付く天皇は、怨霊となることを恐れて贈られたという主張である。確かにこの方々は、やすらかな人生を送ったとは言い難い天皇・皇族である。
ところが、「崇徳院を崇徳と諡したのは、怨霊を恐れたためである」と愚管抄に書いてある。愚管抄も作者の慈円も、井沢元彦はいろいろなところで引用している。にもかかわらず、徳の諡号のオリジナルは慈円だとはどこにも書いていない。
もうひとつ井沢説に瑕疵があるのは、顕徳院をもって「贈徳の字鎮魂法」は終了して、その後徳の字を持つ天皇はいないと書かれているのだが、実は「後文徳院」という天皇がいらしたのである。
顕徳院と同様、後文徳院も諡号が変更され追号となった。後花園天皇と現在呼ばれている。なぜ変更となったかというと、応仁の乱で奈良に疎開中の一条兼良が、「諡号に後を付けた前例はありませんよ(勉強不足だぞお前ら)」と知らせてきたからである。
一条兼良は太閤(前関白)。平安以来の過去の文書を膨大に有していたが、それを応仁の乱で焼かれてしまった。疎開していた先が息子の尋尊のいる興福寺。尋尊は「大乗院日記目録」「大乗院寺社雑事記」の作者・編者である。
崇徳以降顕徳までの諡号には怨霊封じの意味もあったと当時の貴族が書いているし、記録こそ残っていないが文徳、孝徳天皇にもそういう要素があっておかしくない。とはいえ、まったくのオリジナルではないのだから、その旨一言あるのが普通である。学術論文であれば差しさわりがあるといえるだろう。
[Mar 25, 2024]
専門家はやっぱり尊重すべきだと改めて感じる。何十年も井沢元彦はたいしたものだと思っていたが、「贈・徳の字」は彼のオリジナルではなく、平安時代の貴族がすでに書き残したことだった。
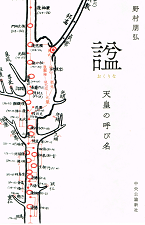
共著者のモントゴメリー&ビクレーは夫婦で、夫が生物科学者、妻が土壌研究者である。それぞれの専門知識だけに偏ることなく、たいへん読みやすく構成されている。
シアトル近郊で住居を購入した夫婦が庭造りするところから始まる。前の住人が園芸に興味がなく、一面の痩せた土だったところに落ち葉や木材チップ、コーヒーかす、たい肥を入れることにより短期間で豊かな土壌にする。なぜこんなに短期間でできたのか。
それは、目に見えるところではミミズなどの小動物だったり、それをエサにする虫や鳥だったりするのだが、それだけではない。バクテリアをはじめとする微生物の力が大きかったのである。
庭の話から、一転して生物の話となる。かつての生物学は動物・植物を中心とした系統樹的な考え方が主で、単細胞の生物がどのように高等動物に進化したかという観点でとらえられていた。
ところが、DNA解析が進み、生物の違いを遺伝子の差によって分類すると、動物や植物を含めたグループは生物の一部にすぎず、細菌や微生物といったグループがそれ以上のスケールであることが判明したのである。
われわれが地球外生物というと、イメージするのは火星人とかE.T.になるけれども、実際にいるとすれば昆虫であり植物であり、もしかすると微生物や細菌は見えないだけで太陽系内にいないとも限らないのである。
ここ百年ほどで、感染症に対する対策が飛躍的に進み、アスピリンやストレプトマイシン、抗生物質により多くの感染症が激減した。これらの開発にも土壌菌が寄与しているのだが、いいことばかりではない。細菌・ウイルスも進化して耐性を身に付けるからである。
こうした特効薬はいざという時のすぐれた対策ではあるものの、健康を維持するためにはそれらとは別に普段の生活を変えていかなければならない。われわれの大腸は園芸における土と同様、数限りない細菌・微生物の住処なのである。
腸内微生物のはたらきによって、われわれの体調・気分を左右するホルモンが出されることが分かってきた。つまり、われわれの体は脳がコントロールしているのではなく、腸に住む微生物がコントロールしているのかもしれない。
だから、特効薬やワクチンで感染症が激減するのと同時に、昨今われわれの脅威となっているのは腸をはじめとする消化器の不調であり、免疫不全である。これらは、腸内環境の不備が原因と考えられる。庭造りにおいて、土が痩せたのと同じ状況である。
この分野の研究も急速に進んでいて、腸内の微生物がどのような分布で、どのような構成になっているかで、肥満や生活習慣病、アレルギーなどの免疫疾患が説明できるという。少なくとも、体内の土であるところの腸内環境を整えることは、人間にとって死活的に重要なことは間違いない。
[Apr 23, 2024]
本題とあまり関係ないが、この本を読んで思ったのは地球外生物はいるんだろうということ。別に火星人や木星人はいなくても、地中奥深くに微生物がいてもおかしくないと思った。
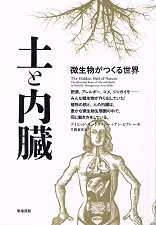
だから、超常現象や超能力については個人的にも深い関心をもっているのだが、オウム事件以来こういう話題は表立って採り上げられなくなった。しかし、スピリチュアルとかメンタリストというように形を変えて、それらへの関心は根強く残っている。
そうした現象に対し、TV受けする採り上げられ方ばかりで、真に科学的な検証がなされていないというのが著者の主張である。
この本でも述べられているように、超常現象とされるもののほとんどがトリックである。仲間由紀恵の言うとおりである。そして普通に考えて、スプーンを曲げられたからそれが何だという話でもある。
動かなくなった時計が動き出すのは熱が加わって機械仕掛けの一部が動くようになるからで、ひな祭りのオルゴールが突然鳴り出すのと同じである。機械でなくて人間でも、火葬しなければ何十人かに一人は生き返って動き出すという話もある。
だから、かつてTVで採り上げられた超常現象の多くは、トリックで説明できる。TV局の目的はちろん視聴率で、目立てばいいというのはつばさの党と同じである。科学的に分析しようという意図もないし関心もない。
、
私が記憶するただ一つの例外は、山倉ダムに死体があるのが見えるという予言者だったが、未解決事件を解決するという特集のほとんどは何もできなかった。
とはいえ、すべての事象が現代科学で証明される訳ではないし、物理学も時代とともに進んでいる。時間も空間もわれわれが思うほど強固ではない。「ありえない」というのは「確率的に小さい」のと同義である。
説明できない事象があるから「霊界」があるという訳ではない(これも本書の中で誰かが言っている)。カウンセリングとか宗教上の理由で、それを持ち出した方が有利だからそう言っているだけである。
それらの玉石混交からすべての石を除いたら玉は残らないのか、それをきちんと分析すべきだと私も思う。いわゆる千里眼的なものは昔からあるし、そのすべてが偶然では片づけられないだろう。
[May 22, 2024]
私の学生当時はホットな話題だったオカルトも、オウム以来めっきり下火になった。また忘れた頃にブームになるかもしれない。
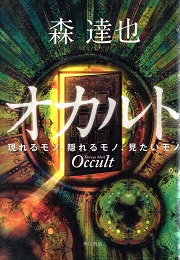
とはいえ、安いものにはそれだけの理由があるというのはデフレ時代からよく言われる。大量生産とか森林破壊で価格が安くなるのは、地球環境には好ましくないが直接の健康被害はない。ところがこの本を読むと、そうでもなさそうなのがよく分かる。
この手の本をあまり読まなかったのは、昔「買ってはいけない」という本があって、それがまた間違いだらけのトンデモ本だったからである。いちばんよく覚えているのは、ソルビン酸とソルビン酸カリウムを混同していたことである。
ソルビン酸は殺菌効果があり厚労省も使用制限を加えているが、だからカリウム塩であるソルビン酸カリウムが危険ということにはならない(保存料として使用されている)。
その論法でいうと、体が溶けるから硫酸マグネシウムや硫酸ナトリウムの混ざったお湯に入ってはいけないことになる。あの本を書いた連中が、打ち上げとか出版記念で登別とか別府に行っていたらお笑いである。
それはともかく、この本もトーンとしては「買ってはいけない」とよく似ているが、内容はかなりまともである。消費者は安いと言うだけで飛びつくけれども、どうやってコストを削っているのか知った上で商品を選ぶべきというのは、その通りだろう。
最初の頃の「美味しんぼ」で、大量生産の醤油や味噌はまともな作り方をしていない。だから保存食品なのに常温保存できないし、栄養価も落ちると指摘されていた。山岡や海原雄山(つまり雁屋哲)が言うまでもないことだが、実はいちばん問題なのは、消費者が化学調味料をおいしいと感じることなのだ。
卵やキャベツは自然のものだから、何かの原因で供給が減れば価格が上昇する。デフレで価格が抑えられて生産者にしわ寄せが来るのは気の毒だが、商品そのものの問題は比較的少ないといえる(農薬や抗生物質の懸念はあるとしても)。
一方で、工業製品として作られている食品には、かなり危ないものが含まれている。この本でも採り上げられているラクトアイスは、原材料として牛乳・生クリームをほとんど使っていない。サラダ油を乳化して、ガムシロップを加えて冷やしたものなのである。
私は昔からコーヒーフレッシュ(スジャータ)を使わないが、ラクトアイスはそれと同じだったのである。知らないというのは恐ろしいことだ。サラダ油とガムシロを食べて喜んでいたとは。
牛乳・生クリームを使わなくても、豆乳やアーモンドミルクで作ったアイスも表記上はラクトアイスになる。しかし、そんな高価な材料は使っていない。100円とかそんな値段で儲けが出るのは、十中八九パーム油を使っているのだ。
パーム油だって原産国では食用だから、あれは石鹸や洗剤で作ってるんですよというのは言い過ぎだが、日本に運ぶまでの間にさまざまな添加物が加えられ、かつ乳化の過程で高温処理されるのでオレイン酸も発生する。アイスクリームというと生クリームを連想するけれど、そんなもの使っていないのである。
他にも、刺身や加工肉、調味料、生鮮食品に至るまで、安く提供するために「これはちょっとひどい」処理がなされている商品はたくさんある。ガザやアフリカの人達と比べると贅沢なのだが、かといって工業製品を食べたくないと思うのは人情であろう。
[Jun 28, 2024]
トーンとしては「買ってはいけない」とよく似ているが、内容はかなりまともである。消費者は安いと言うだけで飛びつくけれども、どうやってコストを削っているのか知った上で商品を選ぶべきだろう。